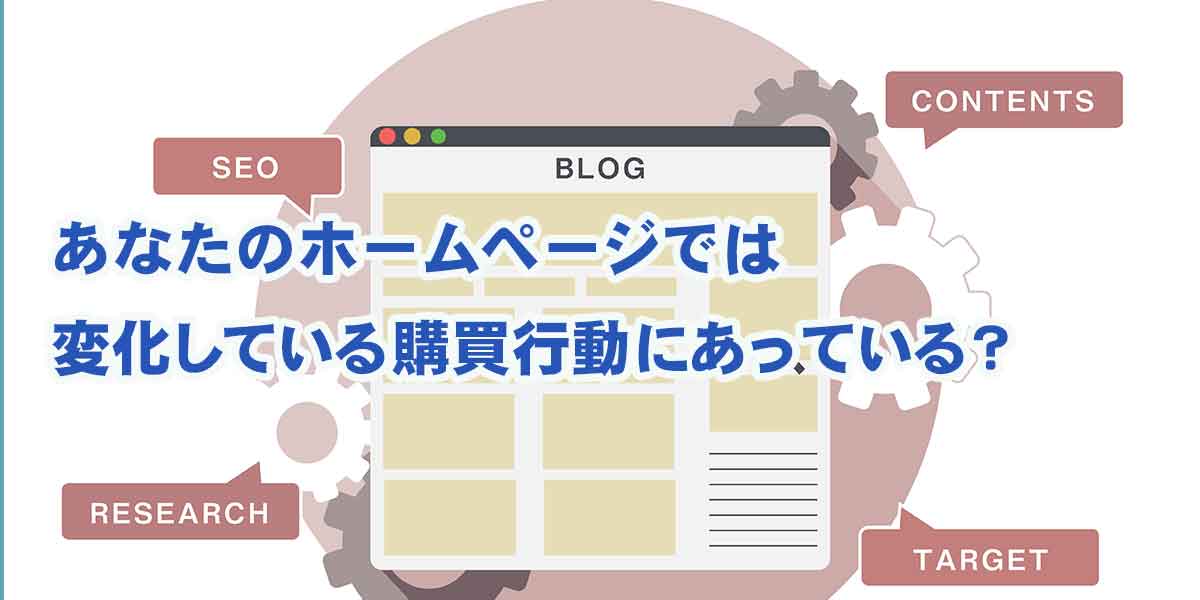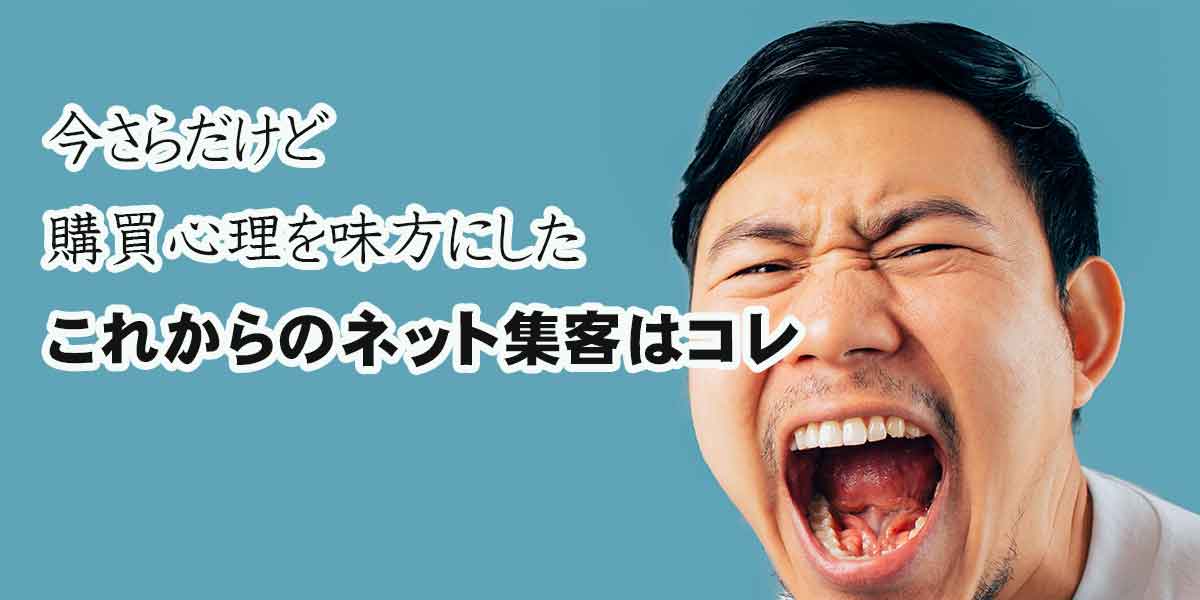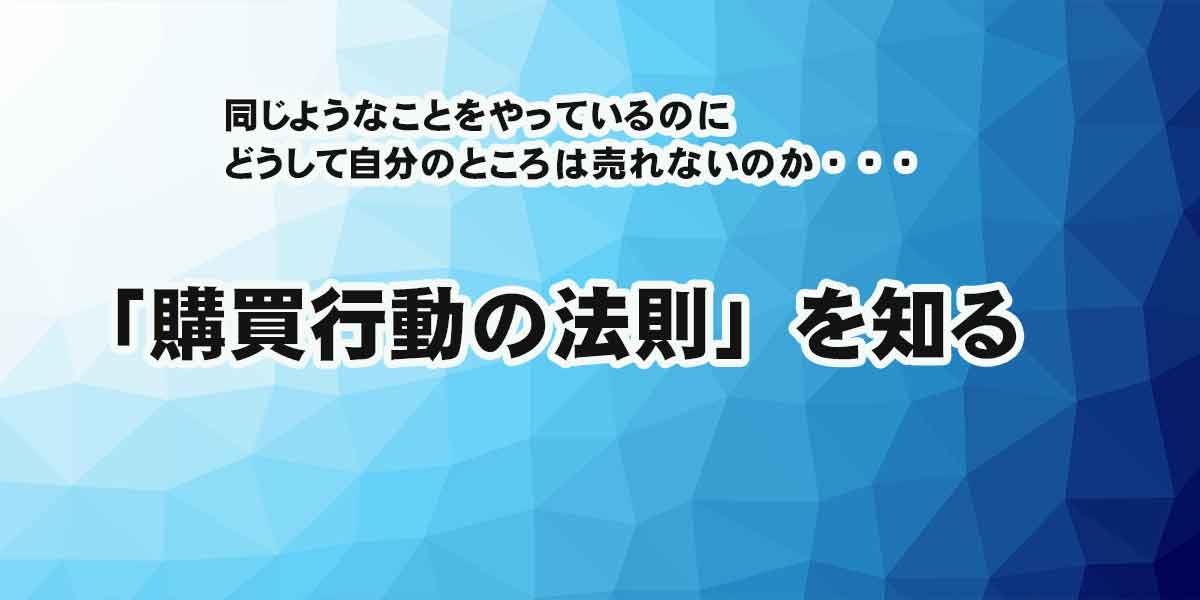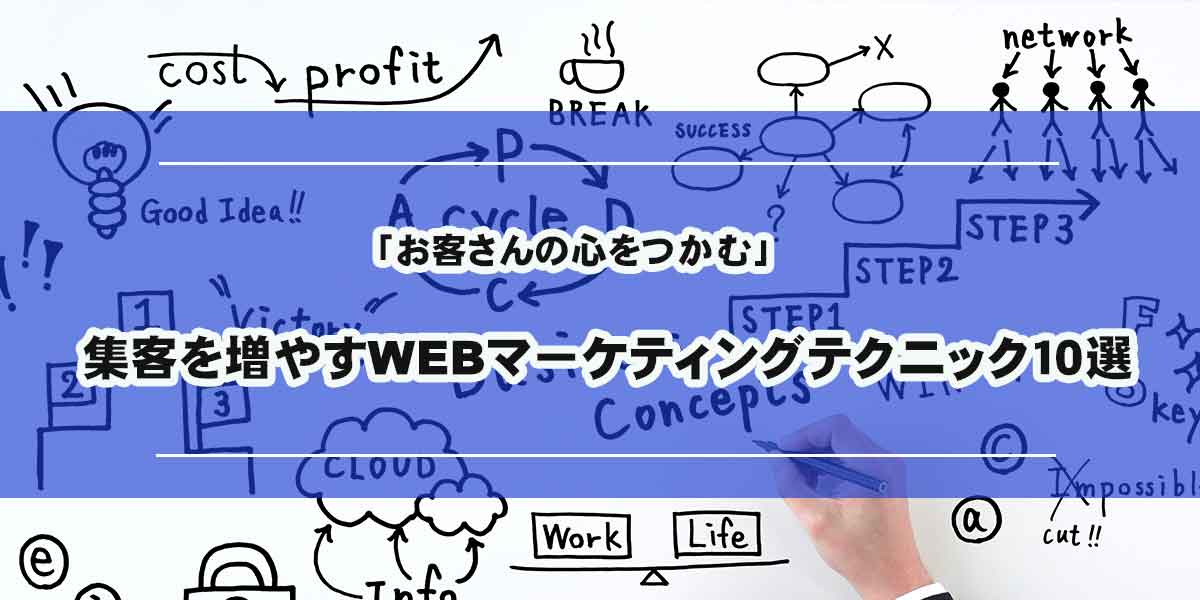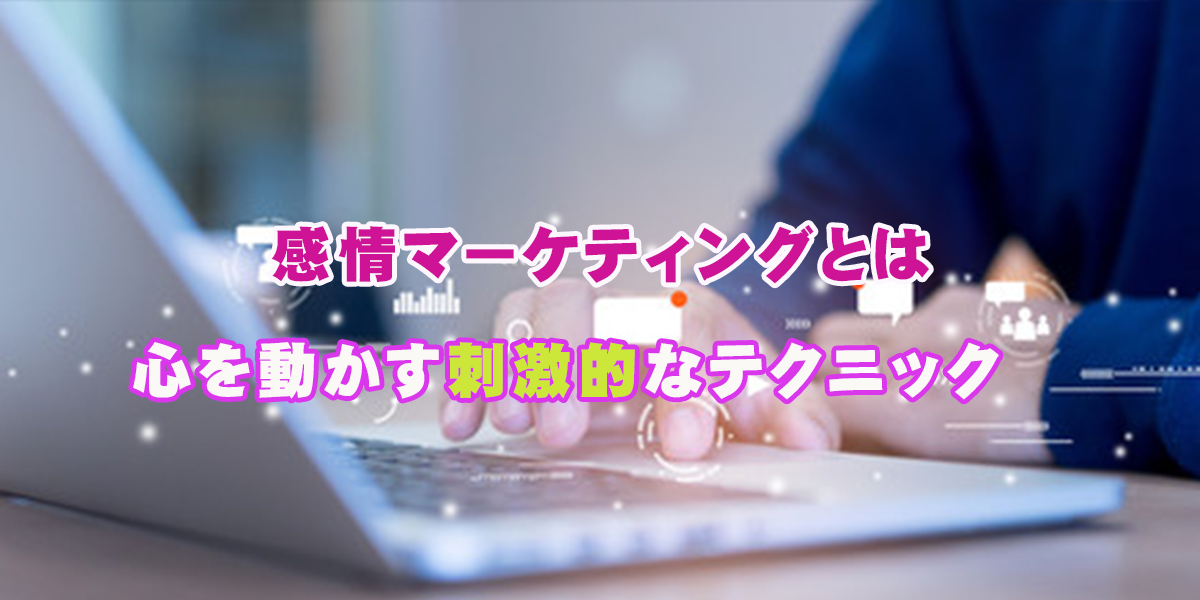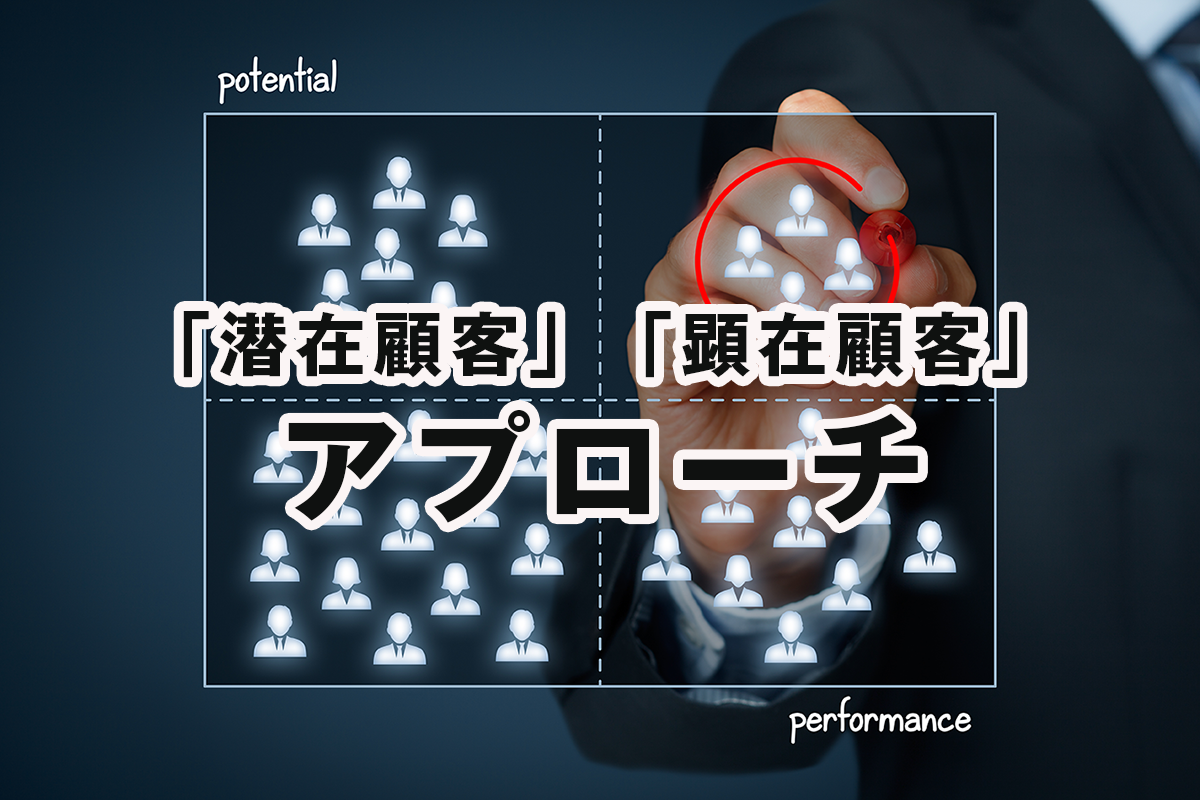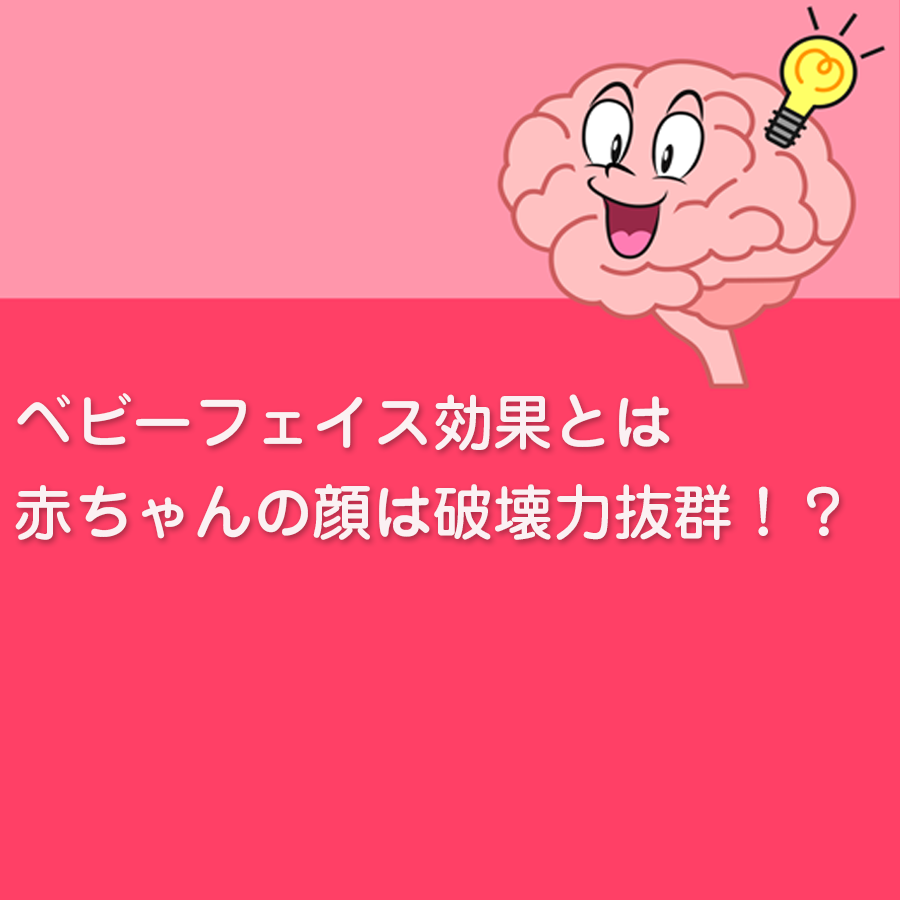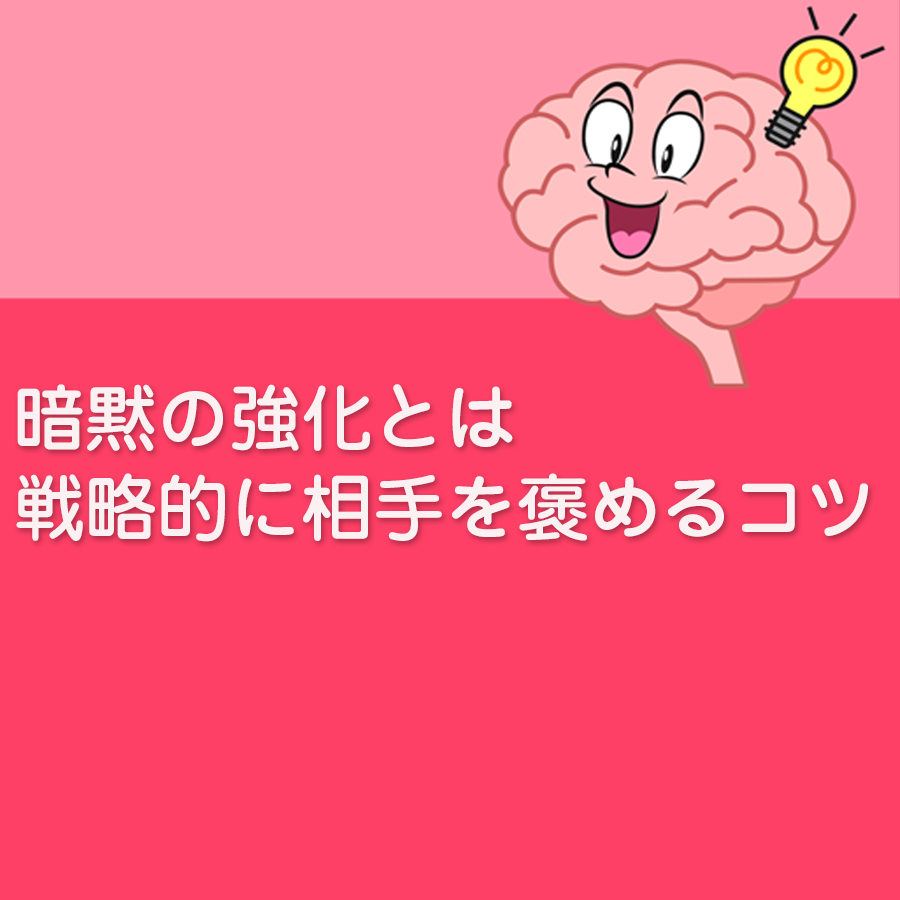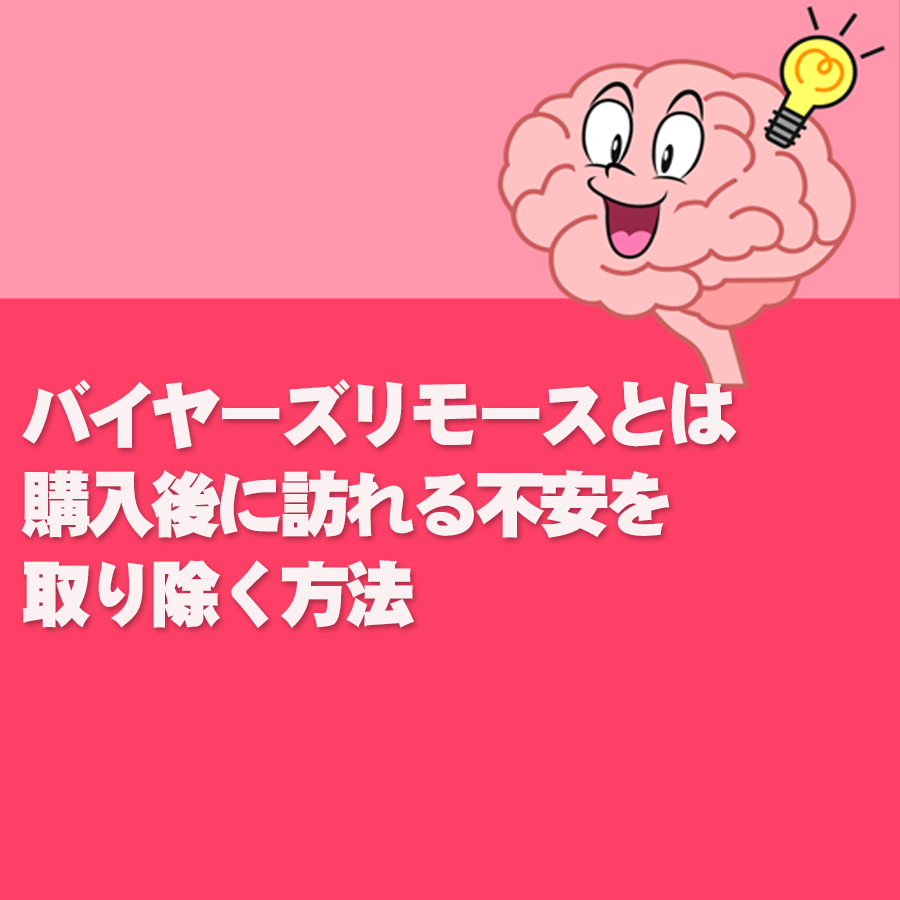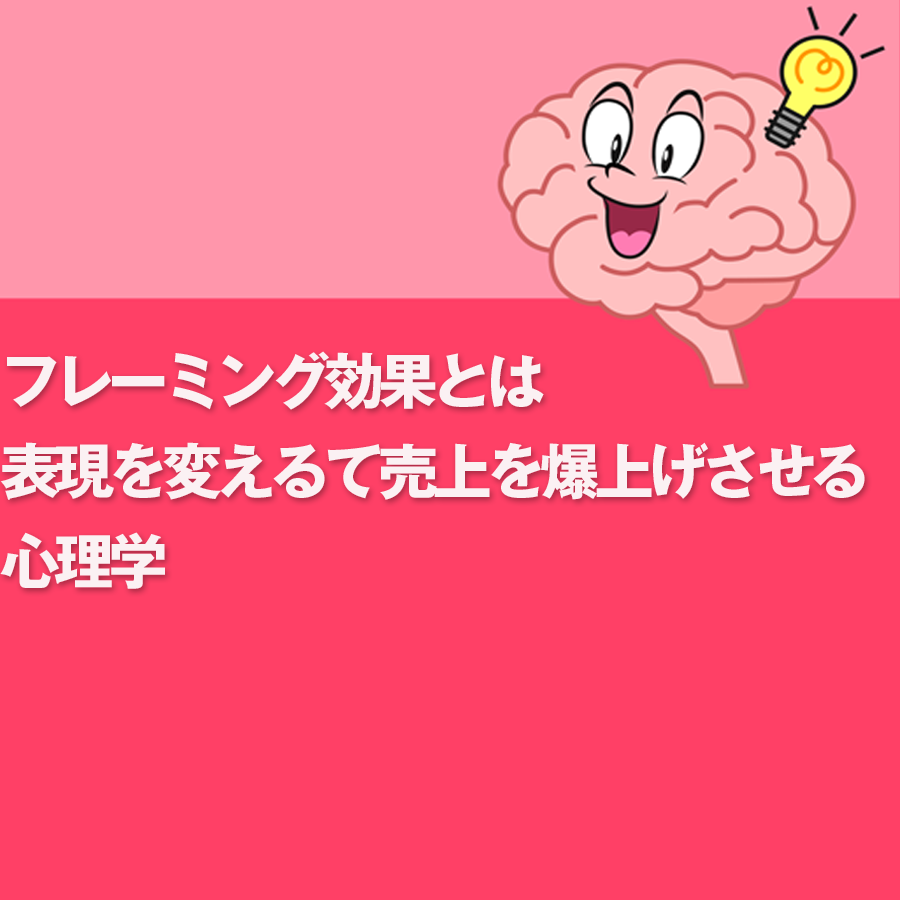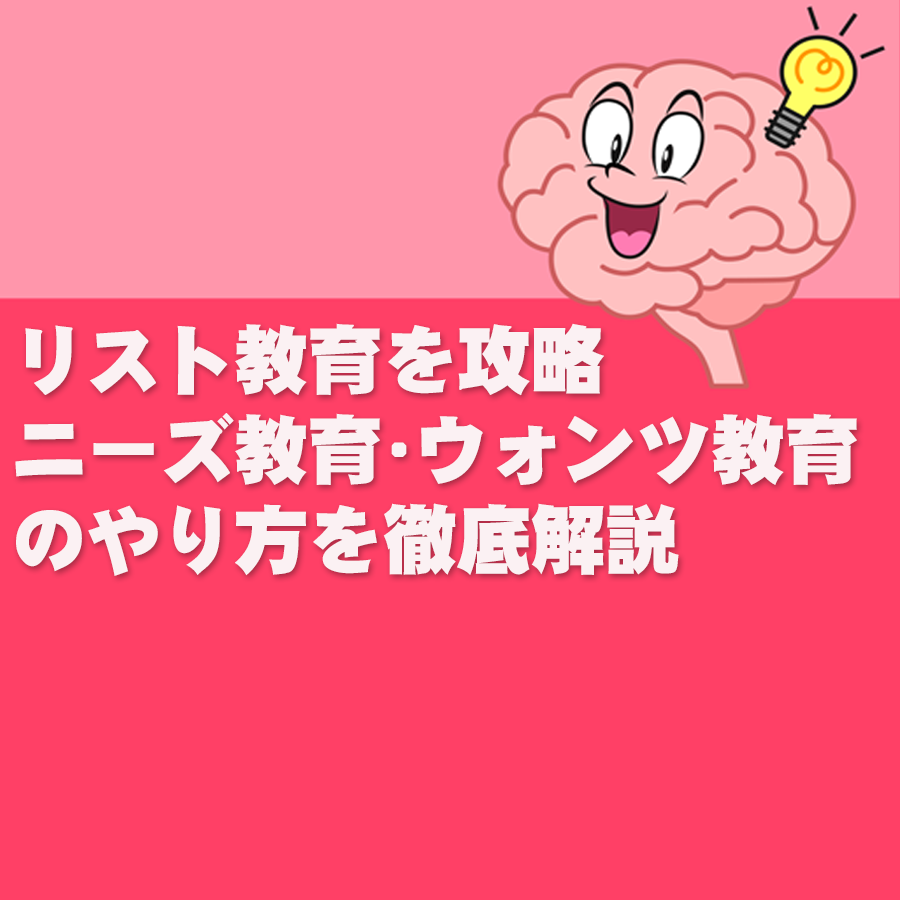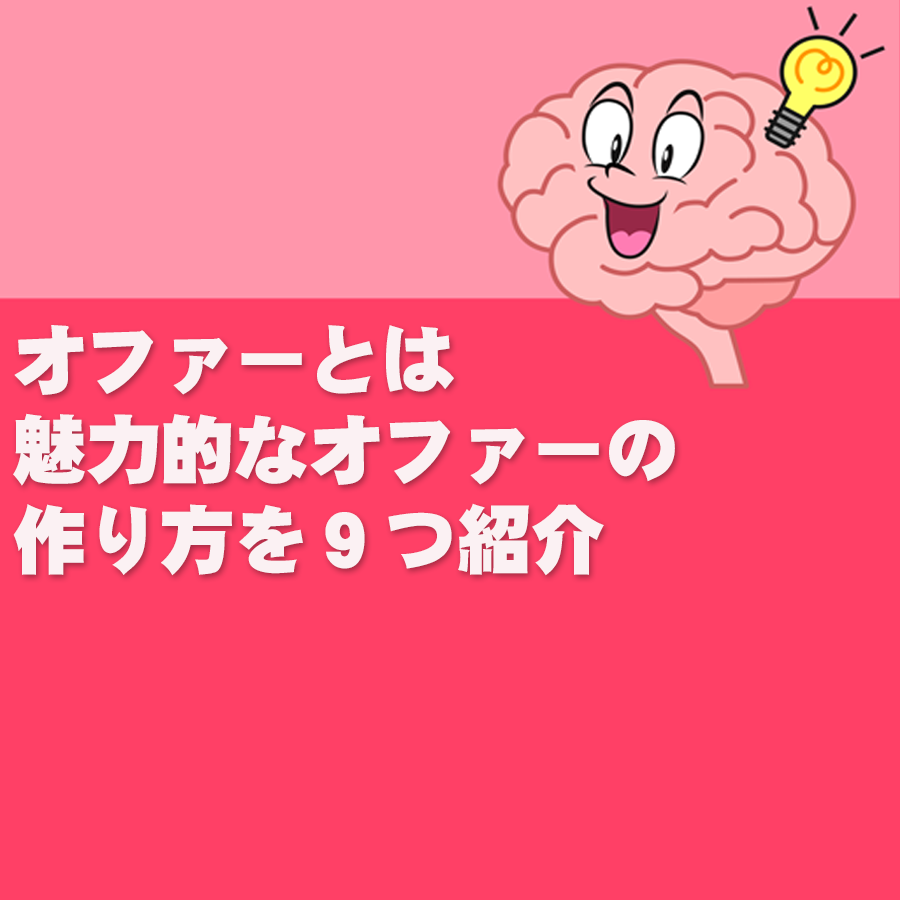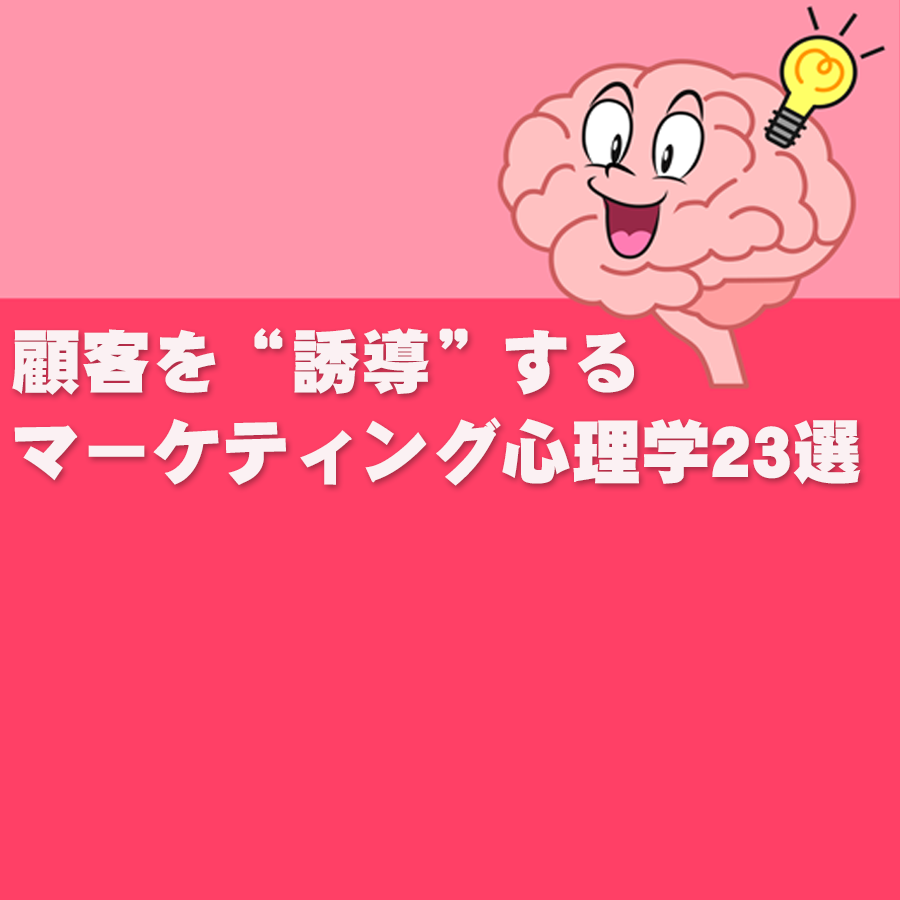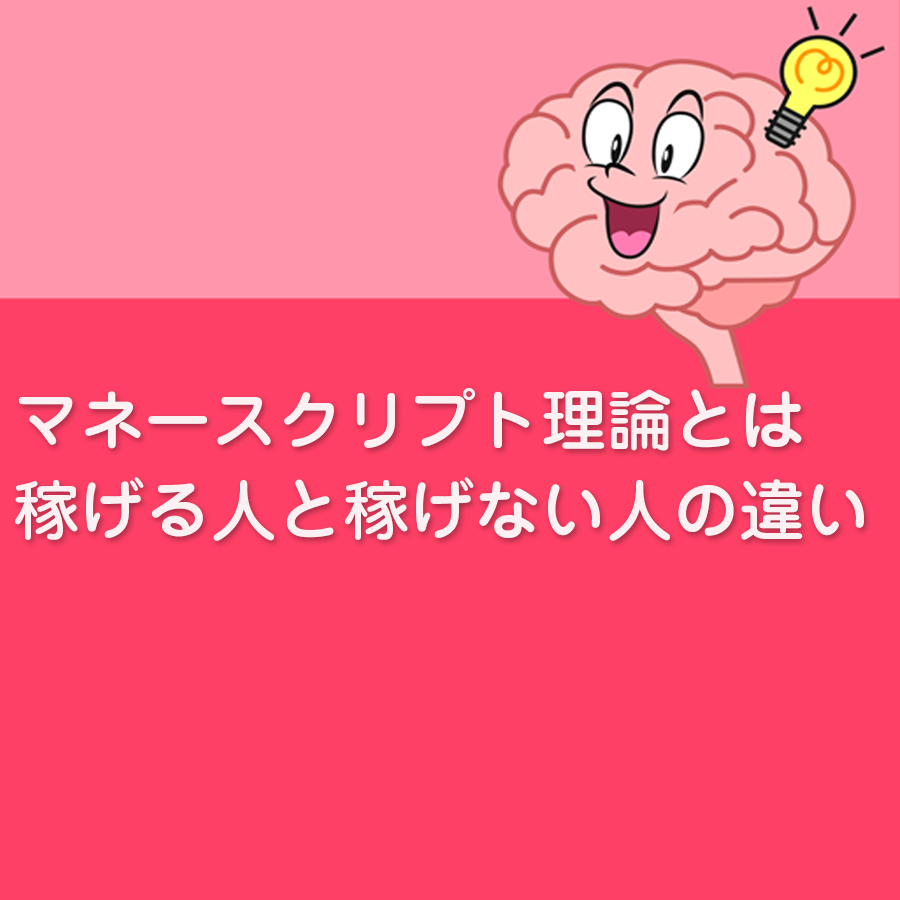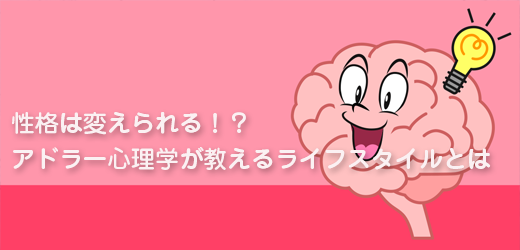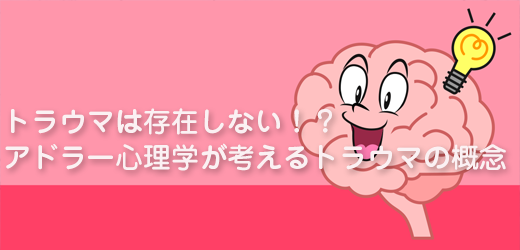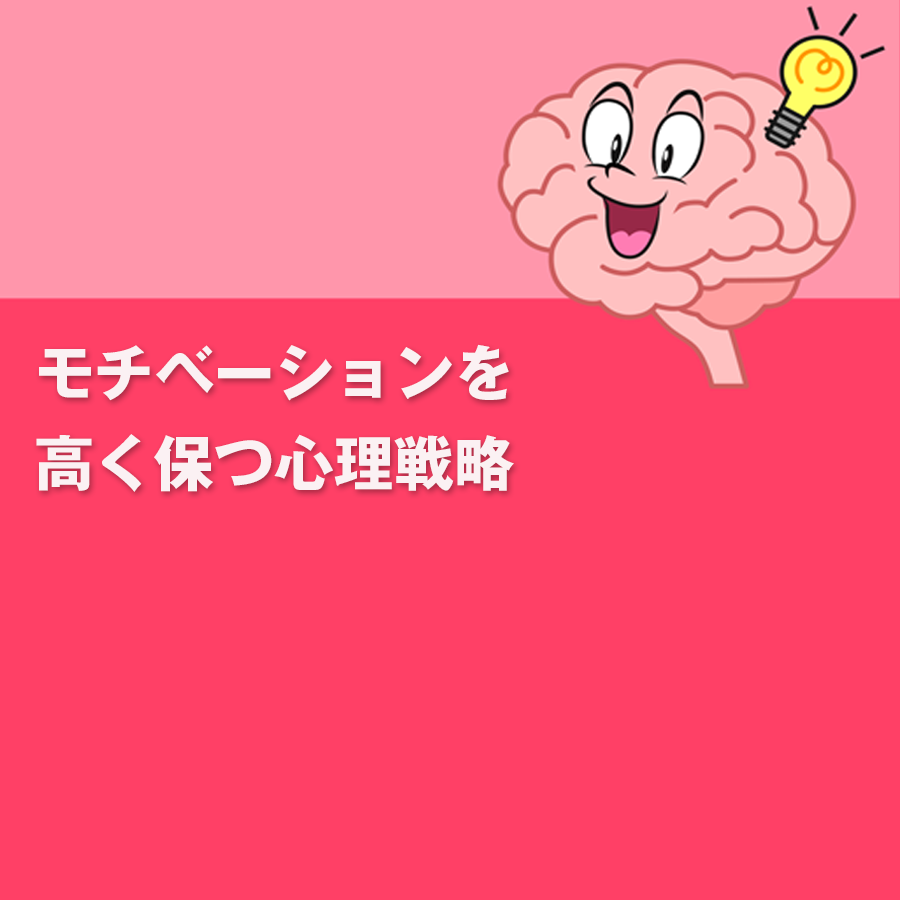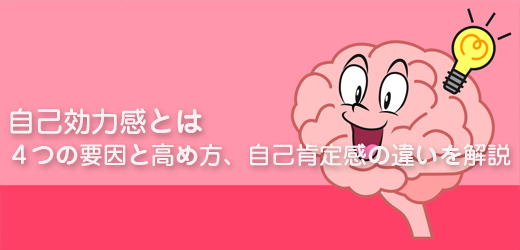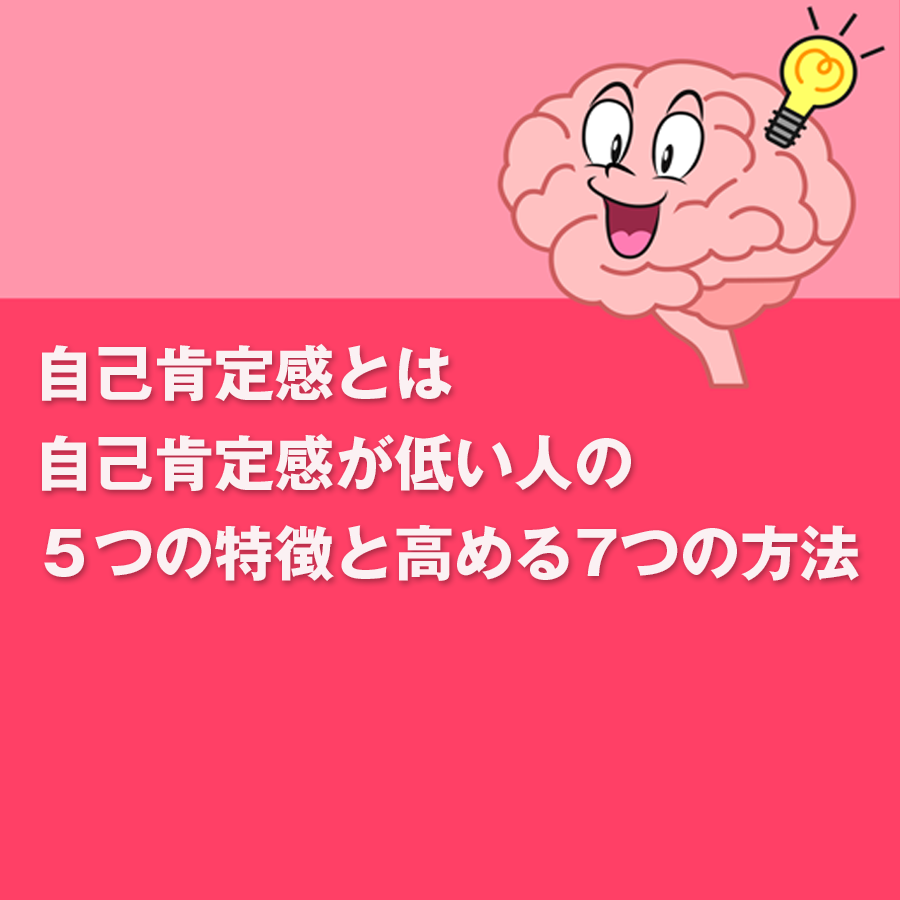(株)ノースメディア
インターネット戦略ブログ|あなたに寄り添う
タグ「心理学」が付いた記事
( 131 件)
-
経営者や個人事業主、フリーランス。一般的に雇用されている人でない限り、莫大な資産をお持ちの方以外は誰でも「売上を上げる具体的な方法」を知りたいものです。 当然ですが、私だって知りたいですし、起業したところの人なら尚更知りたい。また、最近になって競合が増えてきて苦しい状況が見えてきている ●外壁塗装業 ●リフォーム工事業 ●解体工事業 こういった業種の方も、具体的な方法を知りたいはず。 そこで今回は [...]2022.12.28 -
マーケティングと仕事。 どちらにも共通していることと言うと 「相手に影響を与えること」 ●どうしようかと選択に悩んでいる人に影響を与える。 ●ミーティングの出席者に影響を与える。 ●次の行動に影響を与える。 こういった影響を与えたいと誰もが考えていることでしょう。 実のところ、私もそう考えていることがあります。 ほとんどの人が「相手に影響を与えたい」と思っているでしょうし、「自分 [...]2022.11.24 -
「集客がうまくなりたい。」 ビジネスをやっているなら、誰もが思っていることでしょう。 でも、多くの人は「うまくなりたい」と思っていながらも、集客に必要な秘密を知ろうとしていません。 残念ですね。 そこで今回は、集客に必要な秘密である「消費者行動」について紹介します。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 目次 1: 消費者関与を高めろ (1)永続的関与 [...]2019.11.24 -
お客様の購買行動、ちょっと前とは変わったなと感じておられませんか。 そして、自分が商品やサービスを買うときのことを思い出すと、昔とは変わっているなと感じませんか? ご家族やお子さんなども、時代にあわせた買い物の仕方へと変化されていることでしょう。 では、あなたのホームページは、このように変化している購買行動にあっているでしょうか? 今回は変化のスピードが速い、消費者の購買行動について [...]2022.11.24 -
ネットでの集客を考えられたことがありますか? もしあなたが、ネット集客を考えられているのなら、こんなことをお聞きになったことがあると思います。 人がモノやサービスを買うのは『購買心理』からである。 だから購買心理を知ることは、お客様にこちらが思っている通りの行動をしてもらえるということにつながるはず。 そうなれば、安売りする必要もありません。 ライバルとの価格競争に巻き込まれることも減ります [...]2019.11.24 -
「同じようなことをやっているのに、どうして自分のところは売れないのか・・・」 あなたはこんな悩みをお持ちなので、今、この記事を選んで読まれているのだと思います。 実は、この悩みを解消するには、消費者が購入するまでのプロセスを理解しておくことが大切。 そこで今回は、消費者がどういったプロセスを経て購入にたどり着くのか。 その基本となる購買行動の法則を紹介していきます。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ [...]2022.11.24 -
ほしい商品があったとき、昔なら歩いていけるお店だけで決めないと仕方なかったり、お店が集まっているエリアへ行って5〜6件見て回ったりして決めるのが普通でした。 しかしスマートフォンとWi-Fiの普及によってインターネットを使ってほしい商品を探していると、同じ商品を扱っているお店が何十件も出てきます。 ここで次のような問題が浮上してきます。 「同じ商品で同じ価格帯なのに選ばれるショップと、そう [...]2022.11.24 -
ただ形だけのホームページを作って放置する、ただ闇雲にブログに記事を投稿する。 それだけでは、インターネットからお客さんを集めることは難しいでしょう。 もしあなたが、 「ホームページを作っているのにお客さんが集まらない。」 「ブログを更新しているのになかなか集客に繋がらない。」 そんな悩みがあるなら、今回の内容はお役に立てるはずです。 ホームページを使って集客に [...]2022.11.24 -
ビジネスの成長には安定した新規顧客の獲得が必要。しかし、思うように獲得できないのが事実ではないでしょうか。 今回は、これまでホームページやネット広告、FAXDMなど様々な方法をテストしてきたノースメディアが、新規顧客獲得をできるだけ低コストで実践する方法についてお話していきます。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 目次 1: 新規顧客獲得は常に重要 [...]2022.10.22 -
マーケティングを学んでいる人なら、絶対に一度くらいは聞いたことがある「フロントエンド」と「バックエンド」。 マーケティングを進める上では、外すことのできない考え方です。 特にインターネットを使った集客から販売を考えておられるなら、フロントエンドとバックエンドを上手に組み合わせないと、人が集まったとしても売れない状態が続きます。 今回は、間違えやすいフロントエンドとバックエンドで構成するマー [...]2019.09.19 -
マーケティングの中には「感情(エモーション)」を刺激する手法があります。 この手法は、単一の手法としても活用できますが、僕たちとしてはコンテンツマーケティングと組み合わせて使いたいところです。 というのも、感情マーケティングの手法を取り入れることができると、これまで以上に訪問者や顧客との絆を強めることができるから。 知っていて損はありません。今回は「感情マーケティング(エモーショナルマーケ [...]2020.04.16 -
ビジネスを成功へと導くためには、新規顧客の獲得が必要不可欠です。しかし、それだけでは不十分。「潜在顧客」「顕在顧客」へのアプローチも重要です。今回の記事では、ビジネスにおいて、潜在顧客を顕在顧客へ成長させるための正しいマーケティングを導入し、成果へとつながる道筋を整える方法を詳しく解説します。潜在顧客の発見・発掘・獲得から、正しいマーケティングを導入するまでを、一つずつ詳しく説明していきますので、 [...]2022.09.16 -
あなたがこの記事を見ておられるということは、きっとコンテンツマーケティングに興味を持たれているからだと思います。 コンテンツマーケティングは、これまでの売り込み型セールスとは違い、売り込まないセールスだと言えます。 その証拠にノースメディアでは、売り込み型セールスの代表格とも言える ●テレアポ ●FAXDM ●PPC広告 を行っていません。 それでもありがたいことに毎週(毎 [...]2019.09.05 -
令和2年なって、誰も予想できなかったような状況になっています。 外出の自粛、店舗の自主休業。 当然ですが人が移動しないですし、収入や貯蓄への不安が増大しますので、必然的に生活必需品以外の消費は落ち込みます。 このような状況は目の前にあることですから多くの経営者の方たちは、はっきりと「何とかしないと」という危機感をお持ちだと思います。 中には「なんとかなるだろう」と悠長に構えている方のい [...]2022.09.03 -
敵意帰属バイアスとは、他者の言動を“悪意のあるもの”と感じてしまう心理傾向のことです。 ところで、なぜ煽り運転なんていう現象が起こるのでしょうか? 結論、車線変更などで追い越された側が、その行動を「悪意のある行動だ!」と感じてしまうからです。 このように、我々は他者の行動・発言を“悪意のあるもの”と捉える傾向があります。 しかし、なぜこのような現象が起きてしまうのでしょうか? さらに、 [...]2022.01.19 -
後知恵バイアスとは、結果を過大評価し、過去を過小評価するという心理現象のことです。 たとえば、日本VSアメリカのサッカーの試合で「絶対に日本が勝つ!」と予想していたのにも関わらず、 いざアメリカが勝つと「アメリカが勝つと思っていた!」と意見を変えてしまうことがあります。 このように、我々は、目の前の結果を過大評価し、それまでのプロセスを過小評価してしまうという性質を持っています。 しかし [...]2022.01.19 -
フォールスコンセンサスとは、自分の意見や行動が一般的だと考える心理現象のことです。 たとえば、「〇〇ちゃんには甘いお菓子を買って帰ろう〜」とお土産を買ってきたものの、友達は甘いものが好きではありませんでした・・・ こんな経験はありませんか? これは「自分は甘いものが好きだから、〇〇ちゃんも甘いものが好きに違いない!」と無意識レベルで勘違いしてしまった結果生じた現象です。 [...]2022.01.19 -
......................................................................................................メタ認知ってよく使われるけど、なんなの? ............................................................................. [...]2022.01.18 -
バイアスとは、「思考のクセ」のことです。 たとえば、メガネをかけている人に対して、「頭が良さそう〜」と評価してしまうことってありませんか? 実は、これはハローバイアスというバイアスによるものです。 つまり、「メガネをかけている人は、頭がいい!」という思考にクセがあるわけです。 しかし、なぜバイアスについて理解を深める必要があるのでしょうか? というわけで、今回は ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ [...]2022.01.18 -
...................................................................................................................潜在意識・顕在意識という言葉を、一度は聞いたことがあるのではないでしょうか? .............................................. [...]2022.01.12 -
......................................................................................................自分の主張を押し通すのが苦手… 人生で1回でもいいから、相手を論破してみたい… .......................................................... [...]2021.12.15 -
モラル・ライセンシングとは、良い行いをしたら、悪い行いをしてもいいと感じる心理現象のことです。 たとえば、下記のような感じです。 今日は1キロ多めに走ったから、ショートケーキを食べてもいいよね! このように、我々は、良い行いをしたあとは、悪いことをしてもいいという錯覚を起こす傾向があります。 しかし、なぜこのような現象が起こるのでしょうか? というわけで今回は、 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ [...]2021.10.22 -
ベビーフェイス効果(baby-face bias)とは、赤ちゃんのようなキャラクターを見ると、安心感を覚えるという心理現象のことです。 たとえば、「赤ちゃんの画像」が使われている広告を見たことってありませんか? ヤスイも最初そのような広告を見た時に、「何で赤ちゃんの画像を入れるんだろう?」と思っていました。 しかし、意外かもしれませんが、実は「赤ちゃんの画像」はマーケティングにおいてものすご [...]2021.10.09 -
暗黙の強化(Implicit Reinforcement)とは、比較対象を褒める(けなす)ことで、相手がけなされている(褒められている)ように感じる傾向のことです。 たとえば、ヤスイが下記のような発言をしたら、あなたはどう思うでしょうか? .............................................................................. あ [...]2021.10.09 -
ストループ効果とは、2つの異なる認知が干渉し合い、脳が混乱してしまう現象のことです。 たとえば、下記の画像を見て、左から順番に【文字】を答えてください。 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////実験 赤 青 黄 緑 黒 //////////////////////////// [...]2021.10.09 -
----------------------------------------------------------------------------------商品のキャンセルやクーリングオフをもらうことが多い…----------------------------------------------------------------------------------こんな悩みを持ってい [...]2021.03.07 -
フレーミング効果とは、同じ主張でも表現を変えることで、違う印象を受けてしまうという心理傾向のことです。 たとえば、「嫌い!」と言われるよりも、「好きではない」と言われた方が、なぜか軽い印象がありませんか? 他にも、「死亡率10%の手術」と言われるよりも、「成功率90%の手術」と言われた方が手術を受ける気になりますよね? このように、同じ主張でも表現が変われば、全く違う印象を受けることが分か [...]2021.03.01 -
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////マーケティングでの「教育」って一体何をすればいいの?////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////こんな悩みを抱えていないでし [...]2021.02.25 -
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////リストへのオファーがなかなか通らない…////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////こんな悩みを持ってはいないでしょうか?結論 [...]2021.02.25 -
-----------------------------------------------------------------------------------マーケティングって何をすればいいの? 直感でマーケティングしてしまっている・・・----------------------------------------------------------------------------- [...]2021.01.07 -
世の中いろいろな価値観があり人それぞれ違いがあります。さらにいえばお金持ちの人、そうでない人など様々です。残念ながら私たち日本人はお金を稼げない人が多く、貧富の差も拡大してしまってるのが現状です。その根本的な理由として、考え方の違いがあります。一般的にお金を稼げる可能性が高い人、お金持ちになれる可能性がある人には共通した性格があり・真面目でコツコツできる人・誠実性がある人上記に当てはまる人はお金に [...]2020.11.19 -
・自分のこんな性格が嫌だ…・性格は変えられないからなぁ…・もっと明るい性格になりたい…上記のような悩み・疑問を抱えていないでしょうか?実際、現代では「性格は変えることができないものなので、自分の性格にあった仕事に就きましょう!」みたいな風潮もあったりします。それを証拠に、『ビックアフィブ』『ストレングスファインダー』『動物占い』など、その人の本質を探るツールが世の中にはたくさん存在します。つまり、 [...]2020.11.16 -
あなたは何かしらのトラウマを抱えていますか?たとえば、下記のような現象です。・失恋のショックから、女性恐怖症になった…・虐められたショックから、学校へいけなくなった…・犬に噛まれたショックで、動物と触れ合うのが怖い…このように、「トラウマが原因で行動を起こすことができない…」という人は多くいます。しかし、アドラー心理学では「トラウマは存在しない」といっています。(実は、この言い方には語弊があるので [...]2020.11.16 -
課題の分離とは、他者の課題と自分の課題を切り分ける思考法のことです。下記のような経験をしたことはありませんか?たとえば、親が子供に「勉強しなさい!」と説教したとする。きっと普通のことだと感じると思うのですが、実はこの時、親子の間には軋轢が生じる可能性が広がります。なぜなら、親は『勉強する』という子供の課題に介入してしまったからです。そして、自分の課題に介入された子供はきっとこう思うでしょう。「うっ [...]2020.11.16 -
・周りの人と比べると、勉強ができない…・友達には彼女がいるのに、僕にはできない…・誰よりも運動オンチだ…あなたも、何かしらの劣等感を持っていないでしょうか?きっと、生まれてから劣等感を感じたことがないなんて人はいないのではないでしょうか。実際、ヤスイも劣等感を感じることがありました。ヤスイは、極度のあがり症なのですが、初対面であったり2人以上を相手にすると思ったように声が出ません。ぶっちゃけ、ダサ [...]2020.11.16 -
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////・モチベーションが維持できない…・すぐに飽きてしまう…・なかなか目標達成ができない…////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// [...]2020.11.08 -
自己効力感(Self-efficacy)とは、「自分にはできる!」という感情のことです。※自己効力感は、「高い、低い」という表現の仕方をしますたとえば、勉強を例に簡単に説明すると、自己効力感が低い人は、「勉強したところで…」と行動することができません。しかし、自己効力感が高い人は、「よし!勉強しよう!」と行動することができます。このように、「自己効力感が高い・低い」で、「行動する・しない」に大きな [...]2020.11.08 -
自己肯定感(self-esteem)とは、ありのままの自分を受け入れる感情のことです。//////////////////////////////////////////////////////////////////・何に対してもネガティブに考えてしまう…・失敗を引きずってしまう…・自分に自信が持てない…////////////////////////////////////////////// [...]2020.11.08 -
アナウンスメント効果とは、メディアなどの報道が、人々の行動に影響を与える心理効果のことです。たとえば、選挙にて、ある候補者の圧倒的優勢が報じられると、支持者は安してしまい、投票に行くことをやめてしまう可能性が高まります。逆に、ある候補者の圧倒的劣勢が報じられると、支持者は危機感を感じ、投票に行く可能性が高まります。このように、メディアの影響は強烈で、これに人々は大きな影響を受けるのです。というわけ [...]2020.11.07 -
アンダードッグ効果とは、弱い立場の人を応援したくなるという心理現象のことです。たとえば、「売れに売れているアイドルよりも、全く売れず泥臭く頑張っているアイドルを応援したくなる」というのはアンダードッグ効果によるものです。しかし、なぜこのような現象が起こるでしょうか?というわけで今回は☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆1.アンダードッグ効果とは2.アンダードッグ効果をセールスに活 [...]2020.11.07